古い家の売却は、多くの所有者にとって複雑で困難な課題として認識されがちです。新築や築浅の物件と比較すると、市場での評価が低くなる傾向があります。
しかし、適切な知識と戦略を講じることで、円滑かつ納得のいく売却を実現することが可能です。本ガイドでは、古い家を売却する際の多岐にわたる方法、具体的な手続きの流れ、発生する費用や税金について網羅的に解説いたします。
特に、近年進行する空き家問題と関連法改正が売却に与える影響についても深く掘り下げ、所有者が取るべき行動を提示します。
はじめに:古い家の売却、諦める前に知っておくべきこと
古い家の売却は、その特性ゆえに特有の課題を伴います。これらの課題を正確に理解し、適切な対策を講じることで、売却の可能性を大きく広げることができます。
古い家とは?売却が難しいと言われる理由
一般的に「古い家」とは、木造住宅の場合、築20年を超えると市場価値が大幅に下がる傾向があるとされています。特に、税務上の法定耐用年数である築22年を過ぎると、建物の価値はゼロと評価されることが多くなります。
一方で、「古民家」という言葉も耳にすることがあります。これは民俗学的な用語であり、一般的には築50年以上、または昭和25年(1950年)の建築基準法制定以前に建てられた伝統構法の木造家屋を指すことが多いです。古民家は、その歴史的・文化的な価値から、通常の古い家とは異なる需要があり、高値で取引されるケースも存在します。
古い家が売却しにくいとされる主な理由は以下の通りです。
- 耐震基準の問題
1981年以前に建築された家は旧耐震基準に準拠しており、現行基準よりも耐震性が低いと見なされるため、買い手が見つかりにくい傾向があります。購入後の耐震改修費用を買い手が考慮する必要があるためです。 - 資産価値の低下
築年数が古いほど建物の価値は減少し、最終的には土地の価値が売却価格の大部分を占めるようになります。特に、築20年を超えると価格下落が加速し、高値での売却は困難になります。 - 修繕・リフォーム費用の負担
買い手側が購入後に大規模な修繕やリフォームを必要とすることが多いため、その費用が購入のネックとなることがあります。買い手は、物件価格に加えてこれらの費用を考慮に入れるため、総額が高くなりがちです。 - 瑕疵(欠陥)のリスク
目に見えない欠陥(瑕疵)が存在する可能性があり、売却後に発覚した場合のトラブルを買い手が懸念します。2020年4月1日の民法改正により、買主は瑕疵に気づいたタイミングで売主に賠償請求などができるようになったため、売主側のリスクも増大しています。
古い家を放置するリスクと維持費の負担
空き家はたとえ誰も住んでいなくても、所有しているだけで様々な費用が発生します。
具体的な維持費用は以下の通りです。
- 固定資産税
- 都市計画税
- 光熱水費(基本料金)
- 火災保険などの保険料
- 定期的な清掃費
- 専門業者に依頼する場合の管理費用
- 現地へ行くための交通費
これらを合わせると年間10万円~30万円程度の維持費がかかることが一般的です。例えば、土地の固定資産税は小規模住宅用地の特例が適用されても、建物の固定資産税と合わせると年間数十万円に上ることがあります。
さらに、古い家を放置し続けることには、経済的な負担だけでなく、以下のような深刻なリスクが伴います。
放置によるリスク
資産価値のさらなる低下
適切な管理を怠ると建物の老朽化が急速に進行し、屋根や外壁の汚れ、窓ガラスの破損、庭木の繁茂、ゴミの放置などにより、資産価値が著しく低下します。
「特定空き家」や「管理不全空き家」への指定
放置された空き家は、倒壊の危険性、衛生上の問題(害虫・雑草の繁茂)、景観の悪化などにより、自治体から「特定空き家」や、その前段階である「管理不全空き家」に指定されるリスクがあります。
固定資産税の増額
「特定空き家」や「管理不全空き家」に指定され、自治体から「勧告」を受けると、固定資産税が最大で6倍に跳ね上がります。これは、空き家対策特別措置法の改正(2023年6月交付、12月施行)によって強化された措置です。
空き家問題は、単なる個人の資産管理の問題を超え、地域社会の景観悪化、治安悪化、防災上のリスク(倒壊など)といった公共の課題へと深刻化しています。
総務省の住宅・土地統計調査によれば、空き家数は1993年から2023年までの30年間で約2倍となり、過去最多の900万戸に達し、空き家率も13.8%と過去最高を記録しています。
古い家を売却する6つの主要な方法とそれぞれの特徴
古い家を売却する方法は一つではありません。物件の状態、立地、売主の希望(費用を抑えたい、早く売りたい、高く売りたいなど)によって最適な方法は異なります。
ここでは、主な6つの売却方法と、それぞれのメリット・デメリット、適したケースを解説します。
方法1:そのままの状態で売却する(現状渡し)
リフォームや解体などの手を加えず、現在の状態のまま物件を売却する方法です。
メリット
- 売主の費用負担が最も少なく、解体費やリフォーム費が一切不要
- 売却までの期間を短縮できる可能性
- 古民家としての価値を見出す買い手や、DIYを前提とする買い手には魅力的
デメリット
- 物件の状態が悪い場合、買い手が見つかりにくい傾向
- 売却価格が低くなる可能性が高い
- 売却後に瑕疵(欠陥)が見つかった場合のトラブルリスク
適したケース:状態が良い古民家、DIY愛好家向けの物件、とにかく早く費用をかけずに手放したい場合
方法2:古家付き土地として売却する
建物は残したまま、主に土地の価値を評価して売却する方法です。買い手は、購入後に建物を解体して新築を建てたり、大規模なリノベーションをしたりすることを想定します。
メリット
- 売主は解体費用を負担する必要がない
- 買い手は建物の解体時期を自由に決めることができる
- 新築用地を探している層や、土地活用を検討している層もターゲットに加えることができる
デメリット
- 建物自体の評価はほとんどされないため、売却価格が低くなる可能性
- 買い手は購入価格に解体費用を上乗せして交渉してくることが一般的
- 特に「再建築不可物件」の場合、買い手が限定され、売却が非常に困難
適したケース:建物が老朽化しているが解体費用をかけたくない場合、土地の立地が非常に良い場合
方法3:解体して更地にして売却する
古い家を解体し、更地にしてから土地として売却する方法です。
メリット
- 新築用地を探している買い手にとって最も魅力的で、需要が高まる可能性
- 建物の瑕疵リスクがなくなるため、売却後のトラブルを避けられる
- 土地の価値が明確になり、価格交渉がスムーズに進む場合
デメリット
- 高額な解体費用(木造家屋で100万~200万円が相場)が発生
- 解体すると固定資産税・都市計画税が最大6倍に増額されるリスク
- 更地にした後に売却が長期化すると、増額された固定資産税の負担が重くなる
適したケース:土地の立地が非常に良く、新築需要が高いエリア、解体費用を回収できる見込みがある場合
「更地にして売却」は買い手からの需要を高める一方で、固定資産税が最大6倍になるという明確な税務上の負担があります。しかし、この税務リスクを軽減する戦略的な方法として「更地渡し」という概念が存在します。
固定資産税は毎年1月1日時点の土地の状況(建物があるか、更地か)に基づいて課税されます。もし1月1日時点で建物が存在し、その後に売買契約が成立し、物件の引き渡し前に売主が建物を解体して更地で引き渡すのが「更地渡し」です。
方法4:一部リフォームして売却する
キッチンやバスルームなどの水回り、または内装の一部をリフォームしてから売却する方法です。
メリット
- リフォーム済み物件は「すぐに住める家」として買い手にとって魅力的で、高値で売れる可能性
- 内覧時の印象が格段に良くなり、早期売却につながる可能性が高まる
デメリット
- リフォーム費用が発生し、必ずしも全額回収できるとは限らない
- 買い手の好みやライフスタイルに合わないリフォームは、かえって逆効果になることも
適したケース:築年数は古いものの構造がしっかりしており、部分的なリフォームで物件の価値が大きく向上する見込みがある場合
方法5:既存住宅売買瑕疵保険を付けて売却する(インスペクション含む)
売却後に中古住宅に欠陥(瑕疵)が見つかった場合の補修費用を保険で支払う「既存住宅売買瑕疵保険」を物件に付保して売却する方法です。この保険を付保するには、第三者機関による「インスペクション(建物状況調査)」の実施が前提となることが多いです。
メリット
- 買い主は万が一の欠陥に備えられるため、安心して購入でき、売却後のトラブルリスクを軽減
- 建物の信頼性が高まり、買い手が見つかりやすくなる効果が期待できる
- 売主の瑕疵担保責任(契約不適合責任)のリスクを軽減
デメリット
- 保険料やインスペクション費用が発生
- 調査で重大な欠陥が見つかった場合、修繕が必要になる可能性
適したケース:建物の状態に自信があるが買い手の不安を払拭したい場合、売却後のトラブルを避けたい場合
方法6:空き家バンクを活用して売却する
各地方自治体が運営する「空き家バンク」に物件情報を登録し、買い手を見つける方法です。
メリット
- 自治体が運営するため、信頼性が高く、安心して利用できる
- 一般的な不動産市場では売れにくい物件でも、空き家バンクであれば売却できる可能性
- 地方への移住希望者や、地域活性化に関心のある層に直接アプローチできる
- LIFULL HOME’S空き家バンクのように、全国の空き家情報を集約したサイトもあり、広範囲の買い手にリーチできる
- 多くの場合、利用料はかからない
デメリット
- すべての自治体でサービスが提供されているわけではない
- 売却までに時間がかかる傾向
- 自治体によっては、物件の登録に際して最低限の修繕が求められる場合
適したケース:地方の物件、なかなか買い手が見つからない物件、地域貢献に関心がある場合
その他の売却方法
上記の6つの方法以外にも、以下のような選択肢があります。
不動産会社の買取
不動産会社が直接物件を買い取る方法です。メリットとして、仲介よりも早く現金化できる(最短数日~1ヶ月程度)、仲介手数料が不要、売主の瑕疵担保責任が免除される場合が多いといった利点があります。ただし、売却価格が相場より安くなる傾向があります。
隣地所有者への売却
隣地の所有者に直接売却を交渉する方法です。境界問題などが解決しやすく、スムーズな取引が期待できますが、価格交渉が困難な場合や、隣地所有者が購入に興味がない場合は成立しません。
| 売却方法 | メリット | デメリット | 費用負担 | 売却期間 | 適した状況 |
|---|---|---|---|---|---|
| そのまま売却 | 費用負担最小、期間短縮の可能性、古民家需要 | 買い手見つかりにくい、低価格、瑕疵リスク | 低 | 短~中 | 状態が良い古民家、DIY愛好家向け |
| 古家付き土地 | 解体費用不要、新築・土地活用層もターゲット | 建物評価低い、再建築不可物件で困難 | 低 | 中~長 | 建物老朽化、解体費用をかけたくない場合 |
| 解体して更地 | 新築需要が高い、瑕疵リスクなし | 高額な解体費用、固定資産税増額リスク | 高 | 中 | 土地の立地が非常に良い、新築需要が高いエリア |
| 一部リフォーム | 高値売却の可能性、内覧時の印象向上、早期売却 | リフォーム費用発生、費用回収できない可能性 | 中 | 中 | 構造がしっかりしており、部分リフォームで価値向上見込み |
| 瑕疵保険付保 | 買い手の安心感向上、トラブルリスク軽減 | 保険料・インスペクション費用発生、欠陥修繕の可能性 | 中 | 中 | 建物の状態に自信がある、売却後のトラブルを避けたい場合 |
| 空き家バンク | 信頼性高い、売れにくい物件でも可能性、利用料無料 | 全自治体で利用不可、売却期間長期化の傾向 | 低 | 長 | 地方の物件、買い手が見つからない、地域貢献に関心 |
| 不動産会社の買取 | 早期現金化、仲介手数料不要、瑕疵責任免除 | 売却価格が相場より安い | 低 | 短 | 早く売りたい、仲介で売れなかった、トラブル避けたい場合 |
| 隣地所有者への売却 | スムーズな取引の可能性 | 価格交渉困難、隣地所有者の意向次第 | 低 | 短~中 | 隣地所有者が土地の拡大や活用を検討している場合 |
古い家売却の具体的な手順と流れ
古い家を売却するプロセスは、いくつかのステップに分かれます。平均的な売却期間は、売却活動開始から売買契約締結までおおむね3ヶ月程度が目安とされています。これは、不動産会社との媒介契約期間が通常3ヶ月であることが業界の目安となっているためです。
ここでは、売却を成功させるための具体的な手順を追って解説いたします。
ステップ1:不動産売却の相場を把握する(数日~1週間)
適切な売却価格を設定するために、まず周辺の不動産相場を把握することが非常に重要です。相場よりも高すぎる価格設定は売れ残りの原因となり、逆に安すぎる価格設定は売主の損失につながる可能性があります。
自分で相場を調べる方法として、以下のような手段があります。
- 不動産ポータルサイト(例: SUUMO, LIFULL HOME’S)で類似物件の売出価格を調査
- 国土交通省の「不動産取引価格情報検索」で過去の成約事例を参考
- 近隣の不動産会社への簡易ヒアリング
ステップ2:複数の不動産会社に査定を依頼する(1週間~2週間)
信頼できる不動産会社を見つけることが、売却成功の鍵を握ります。不動産査定には、以下の2種類があります。
机上査定(簡易査定)
データのみで査定する方法で、短期間で概算の査定額を知りたい場合に適しており、即日~数日で結果が出ます。
訪問査定
担当者が実際に物件を訪問して詳細に査定する方法で、より正確な査定額を知るために必要で、1週間~2週間かかるのが一般的です。
複数の不動産会社(少なくとも2~3社)に査定を依頼し、査定額だけでなく、その根拠や売却戦略、担当者の対応などを比較検討することが推奨されます。
一括査定サービス(例: HOME4U、すまいValue、SUUMOなど)を利用すると、効率的に複数社へ依頼できます。
特に古い家の売却においては、古民家やボロ家の売却実績が豊富な不動産会社を選ぶことが重要です。
ステップ3:売出価格を決定し、媒介契約を締結する(1日~1週間)
複数の査定結果を参考に、不動産会社と相談しながら、最終的な売出価格を決定します。売出価格が決まったら、不動産会社と「媒介契約」を締結します。
媒介契約には、以下の3種類があります。
- 専属専任媒介契約
1社のみに売却を依頼し、売主は自分で買い手を見つけることができません。 - 専任媒介契約
1社のみに売却を依頼しますが、売主は自分で買い手を見つけることができます。 - 一般媒介契約
複数社に売却を依頼することが可能です。
契約期間は、いずれの媒介契約においても一般的に3ヶ月が目安とされています。
ステップ4:購入希望者が見つかったら売買契約を締結する(1~3週間)
媒介契約を締結後、不動産会社が中心となって売却活動を行います。
具体的な売却活動内容は以下の通りです。
- 不動産ポータルサイトへの物件情報掲載
- 住宅情報誌への掲載
- 新聞の折り込みチラシ
- 物件近隣でのチラシ配布
- 購入検討者リストに載っている顧客への連絡
内覧対応時には、誠実な態度で臨み、物件の状況を正確に伝えることが重要です。購入希望者が見つかったら、価格や引き渡し時期、付帯設備の取り扱いなど、細かい契約条件を交渉し、合意に至れば売買契約を締結します。
契約に先立ち、不動産会社の担当者から買主に対して「重要事項説明」が行われます。これは売却する物件に関する法的な内容を含むため、不明点があれば必ず質問すべきです。
ステップ5:引き渡しと確定申告(1~2ヶ月)
売買契約で取り決めた引き渡し日に、買主は売買代金の残金を決済し、売主は物件の鍵と関連書類を引き渡します。同時に、司法書士が所有権移転の登記手続きを行います。
不動産を売却して利益(譲渡所得)が出た場合は、翌年に確定申告を行う必要があります。
| ステップ | 期間目安 | 主な活動内容 |
|---|---|---|
| 査定の依頼 | 1~2週間 | 不動産会社選定、机上査定・訪問査定の実施、査定結果の比較 |
| 不動産会社との契約 | 1日~1週間 | 媒介契約の種類選択、売出価格の最終決定、契約締結 |
| 売却活動・内見対応 | 平均3ヶ月 | 物件情報掲載、広告活動、購入希望者への内見対応、価格交渉 |
| 売買契約・住宅ローンの審査待ち | 1~3週間 | 重要事項説明、売買契約書作成・締結、買主のローン審査 |
| 物件引き渡し | 1~2週間 | 残金決済、鍵・書類の引き渡し、所有権移転登記 |
古い家売却にかかる費用と税金、利用できる特例
古い家の売却には、売却益が出た場合に発生する税金だけでなく、様々な費用がかかります。これらの費用や税金、そして利用できる税制優遇措置を事前に把握しておくことで、手残りを最大化し、計画的な売却が可能になります。
売却時に発生する主な費用
古い家を売却する際には、以下のような費用が発生します。
仲介手数料
不動産会社に売却を依頼した場合に支払う費用です。宅地建物取引業法で上限が定められており、一般的に「売却価格×3%+6万円+消費税」が上限となります。
印紙税
売買契約書に貼付する収入印紙の費用で、契約金額に応じて税額が異なります。
解体費用
更地にして売却する場合に発生する費用です。木造家屋の場合、100万~200万円が相場とされています。自治体によっては、空き家の解体費用に対する補助金制度を設けている場合もあります。
測量費用
土地の境界が不明確な場合、確定測量が必要となり、その費用が発生します。
司法書士費用
所有権移転登記や抵当権抹消登記などの法的手続きを司法書士に依頼する際に発生する費用です。
その他の費用
不要な家財やゴミの撤去費用、一部リフォームして売却する場合のリフォーム費用、既存住宅売買瑕疵保険料やインスペクション費用などが挙げられます。
譲渡所得税とは?計算方法と注意点
不動産を売却して利益(譲渡所得)が出た場合に課される税金で、所得税(+復興特別所得税)と住民税の総称です。
計算式
譲渡所得 = 売却価額 - (取得費 + 譲渡費用)
取得費
物件の購入代金、購入時の仲介手数料、印紙税、登記費用など、購入にかかった費用全般を指します。
譲渡費用
売却時の仲介手数料、印紙税、測量費用、解体費用など、売却にかかった費用全般を指します。
注意点:古い家の場合、購入時の契約書などが残っておらず、取得費が不明なケースが少なくありません。この場合、売却価額の5%を取得費と見なして計算される「概算取得費」が適用されます。これにより譲渡所得が大きな値で算出されることから、支払う税額が高くなる可能性があるため、可能な限り購入時の書類を探し出すことが節税対策として非常に重要です。
利用できる税制優遇措置
古い家の売却時に利用できる税制優遇措置は複数存在し、これらを活用することで税負担を軽減できます。
3,000万円特別控除(居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除の特例)
自分が住んでいたマイホーム、または相続した古い家を売却した場合に、譲渡所得から最大3,000万円まで控除できる特例です。
計算式:譲渡所得 = 売却価額 - 取得費 - 譲渡費用 - 3,000万円
低未利用土地等を譲渡した場合の特別控除の特例(100万円特別控除)
売却価格が500万円以下の古い家(低未利用土地等)で、特定の条件下(長期譲渡所得に該当するなど)で利用できる特例です。譲渡所得から100万円を控除できます。
譲渡損失の損益通算と繰越控除の特例
不動産の売却で損失が出た場合に、他の所得と相殺したり、翌年以降3年間繰り越して控除したりできる特例です。
被相続人の居住用財産(空き家)を売ったときの特例
相続した空き家を売却した場合に適用される特例で、一定の要件を満たせば3,000万円まで控除できます。この特例は、令和9年(2027年)12月31日までの売却が条件の一つとなっています。
| 費用項目 | 費用の目安 | 発生タイミング | 補足事項 |
|---|---|---|---|
| 仲介手数料 | 売却価格の3%+6万円+消費税(上限) | 売買契約成立時、引き渡し時 | 売却価格が低いほど割合が高くなる傾向 |
| 印紙税 | 契約金額による(例:100万円超500万円以下は2,000円) | 売買契約書作成時 | 契約書に貼付する収入印紙代 |
| 解体費用 | 木造家屋で100万~200万円 | 売却前、または引き渡し前(更地渡しの場合) | 自治体による補助金制度の可能性あり |
| 測量費用 | 数十万円~100万円以上 | 売却活動開始前 | 境界が不明確な場合に必要 |
| 司法書士費用 | 数万円~数十万円 | 引き渡し時(所有権移転登記など) | 登記手続きを専門家に依頼する費用 |
| 家財撤去費用 | 数万円~数十万円 | 売却活動開始前、または引き渡し前 | 不要な家財やゴミの処分費用 |
| リフォーム費用 | 数十万円~数百万円 | 売却活動開始前 | 物件の状態やリフォーム内容による |
| 既存住宅売買瑕疵保険料・インスペクション費用 | 数万円~数十万円 | 売却活動開始前 | 買い手の安心感を高めるための費用 |
複雑な税制の存在は、個別状況に応じた最適解の変動を生み出し、素人判断の困難さを増幅させます。このため、専門家(税理士、不動産会社)の必要性が高まり、適切な税務処理と最大限の節税が実現されることになります。
古い家の売却における税金対策は、単に控除額を知るだけでなく、自身の状況に最も有利な特例を特定し、その適用条件をクリアするための専門知識が不可欠です。特に、取得費が不明な場合や、複数の特例が絡む複雑なケースでは、不動産会社だけでなく、税理士などの税務専門家へ相談することが、手残りを最大化するための極めて重要な戦略となります。
まとめ
古い家の売却は複雑なプロセスですが、適切な知識と戦略により、納得のいく売却を実現することが可能です。
本ガイドで解説した「そのまま売却」「古家付き土地」「更地化」「一部リフォーム」「瑕疵保険付保」「空き家バンク活用」の6つの方法から、物件の状態と立地、ご自身の希望に最も適した方法を選択することが重要です。
また、2023年の空き家対策特別措置法改正により、放置によるリスクが大幅に増大しているため、早期の行動が求められます。
売却を成功させるためには、まず複数の不動産会社への査定依頼から始めましょう。複雑な税制や費用については、不動産会社だけでなく税理士などの専門家への相談も検討することをお勧めします。
適切な準備と専門家の活用により、思っていた以上に良い条件での売却が実現できる可能性があります。まずは行動を起こし、後悔のない売却を目指しましょう。



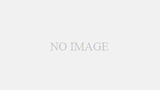
コメント